やかんです。
明後日に英米法の試験がありますね。頑張っていきます。
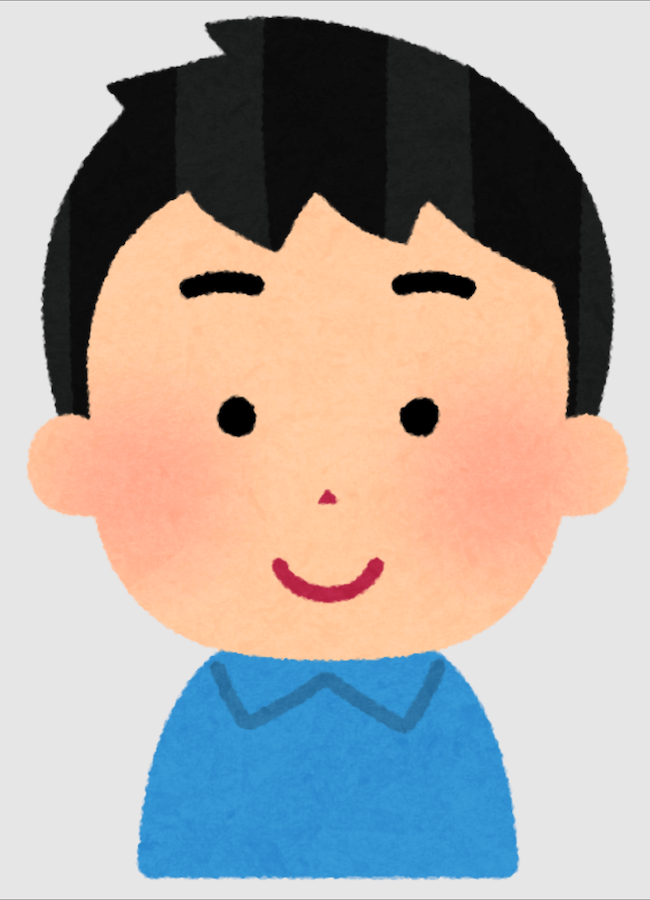
※内容は僕のパブリックメモです。
英米についてもっと理解したい
なんか、最近英米法がいっそう面白くなって参りました。いや、高校時代に世界史勉強しておいてよかったです。
物理化学を勉強できてないのが残念だなー、と思ってましたが(だから今勉強中です)世界史地理(あとちょっと日本史)を勉強できていたのはめちゃよかったなって最近思います。
議院内閣制と大統領制を比較する
まずそれぞれについて簡単に述べます。議院内閣制から。
議院内閣制は、行政(執行府)の立法府に対する信任が必要な体制。言い換えると、立法府は、自分たちが作った法律を行政が上手に運用しない場合、「お前ら役不足じゃ!」ということで物申すことができるわけです。
この時、行政を内閣、立法府を議会が担う感じですね。
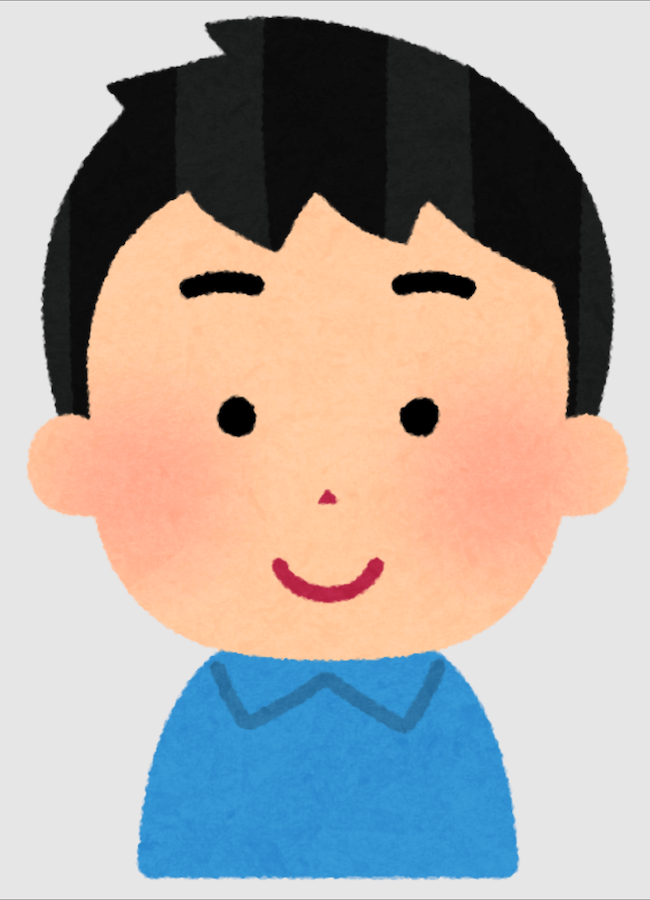
全然正確ぢゃない、ごめんなさい
大統領制はこの逆として考えるとスッキリ感あって、立法府は、行政がとんでもなくポンコツでも「お前ら役不足じゃ!」と物申すことができないわけです。
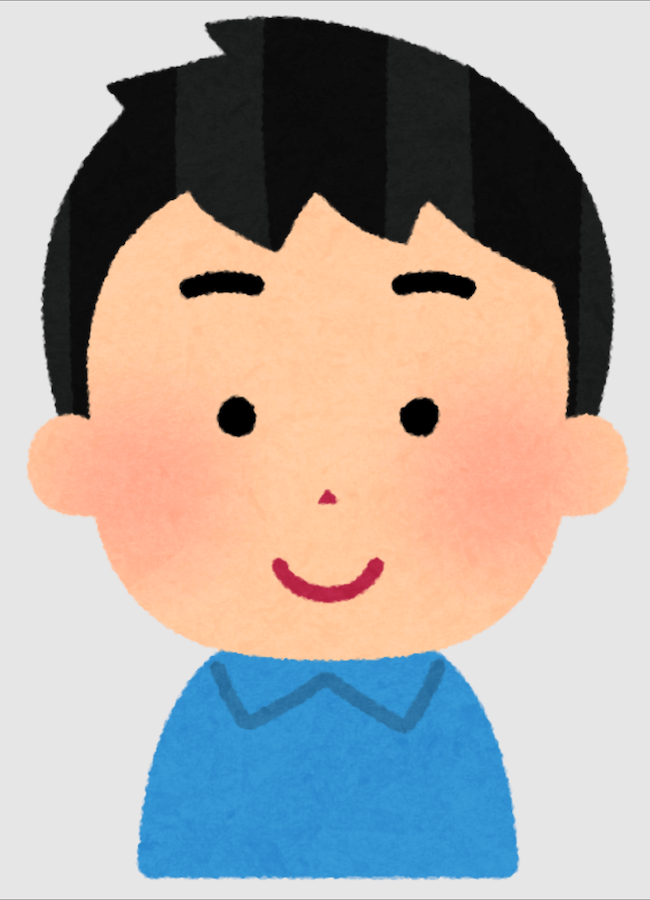
「できない」は言い過ぎです。物申すための仕組み自体はありますが、議院内閣制に比して強権的でない、ということです。
で、行政は大統領中心で、立法府は議会て感じです。
アメリカにおける連邦裁判所と州裁判所の違い
まず前提として、アメリカは連邦制なので、州裁判所の方が連邦裁判所よりも管轄権が広いです。
裁判官の選任方法としては以下。
- 連邦裁判所:大統領による指名、上院による承認
- 州裁判所:立法府による選挙、執行府による任命
で、この州裁判所における裁判官の選挙に関して百選64だよな。裁判官に関して「現実の偏見の可能性」があれば、利益相反を認めて良い、みたいな話だ。
イギリスにおけるConstitutional Reform Act 2005について
もはや「英米について理解したい」の内容ではないが、ここで見ておく。
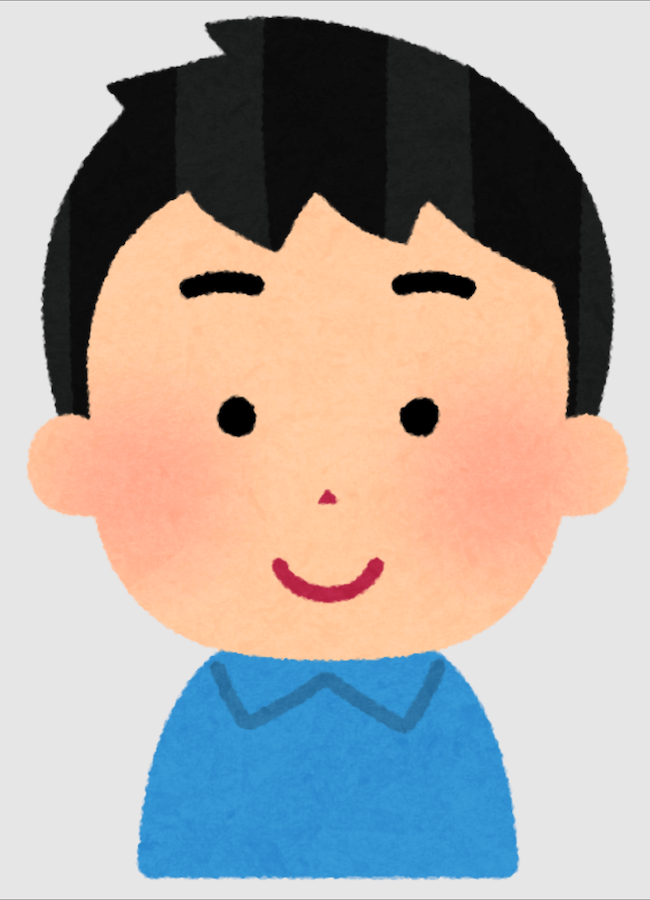
もうぐっちゃぐちゃ
まず大枠は、Lord Chancellorが強すぎたから権力抑えた、みたいな話だ。
Lord Chancellor(大法官)は当時、Chancery(大法官府、equityの裁判所)長官であり、House of Lords(貴族院)の議長であり、かつ内閣にも属していためちゃつよピーポーだった。
これがガンジー島を巡る争いの中で顕在化して、「いや、三権分立した方がええやろ」ってことで是正を図る改革がなされた。それがConstitutional Reform Act 2005だと理解している。
ていうのを踏まえて、契約法などについて見ていきたい。
契約法
まず、契約の成立について
- 約因法理:約因の提供があった場合に契約の成立を認める(comon law)
- 約束的禁反言:片方の信頼に保護の要請がある場合は契約の成立を認める(equity) ← 例外
- 捺印契約:約因法理、約束的禁反言において契約の成立が認められない場合でも、捺印があれば契約の成立を認める
というような3つの契約成立パターンがあると理解しているのだけど、これはあっているのだろうか?
捺印契約については形式性が強いから、特に論点はないはず。で、約因法理と約束的禁反言については相互に関連付けて理解するのが良いと思われる。
約因法理と約束的禁反言の関係について
約因法理においては、約因が提供された約束について契約の成立を認めるという考え方が採用されるが、約因が提供されていない約束については契約の成立を認めないのか、という問題が生じる。
これについては百選96を見ると良い。
百選96(Drennan v. Star Paving Co.)
前提として、約束的禁反言というのはcommon lawではなくequityの法理です。これが、契約法(common lawがメイン)においても妥当する場合があるよ、という点でこの議論は画期的なわけだと理解しています。
まず判旨を引用。が、特殊文字は#で代用することにする点留意されたいです。
約因がなければ必ず、約束が無効になるのではない。#90の目的は、交換に基づく約因がなくても、その申込みにより当然の信頼が引き起こされている場合には、それを、不正を防ぐため、約因の代わりとすることである。
なるほどって感じですね。また、これについては例の如くNotes(解説)が非常にわかりやすいです。
入札がなされ、まだ結論が出ていない状態というのは入札申込みという約束だけが存在し、それが承諾される保証もなく、約因にも支えられていないという状態である。そのような約束に法的効力はあるか?あるとすればなぜか?それがこの事件の争点である。
なるほど。とてもわかりやすいです。
約束的禁反言というのは、equityに属す法理であるということからもなんとなくイメージできるように、商事取引などにおいては用いられることがなかったらしいです。また、かなり飛ばして以下にNotesを引用します。
その後の判例では、この原則は、約因理論では契約が成立しているとは言えない場合であっても、約束に効力を認めないと当事者間に著しい不均衡を生じる場合に、約因の代わりに契約成立要件として使用されるようになってきている(Universal Computer Sys. V. Medical Servs. Assiciation(3d Cir. 1980))。
契約の文言解釈について
英米法の契約については、「とにかく契約にあらゆるケース想定して明記しろ」という立場であると理解している。force majeure clause(不可抗力条項)に顕著な気がする。
これについては、契約法の文脈であることは間違いないが不法行為の文脈でどうせまた見ることになるので一旦飛ばす。
契約についての救済
契約があるということは、それに対する救済が考えられるべきである、ということだと理解している。で、契約法は原則的にcommon lawの分野に属するので、救済としては損害賠償が原則である。
というわけで、損害賠償として何を観念しますか、みたいな話がまず登場する。
これは日本民法みたいな話になるのだが、以下の3つを考えれば良い。
- 履行利益
- 信頼利益
- 原状回復利益
で、これについては百選101に詳しいが、ざっくり述べると「契約についても信頼利益でいいよ(履行利益、原状回復利益は両極端だから)」ということだと思っている。ちょっと、これ以上深掘る元気がないので、飛ばす。
また、契約の救済方法としてequity上の救済も観念される点にも着目したい。すなわち、特定履行と差し止め。どういう場合にこれらが活用されるのかはちょっとわからないが、common lawではまず見られない救済措置だよね。
損害の考え方として一般損害、特別損害の議論もあるが、これは省略していいかな?特別損害を観念したいのであれば、「こういう損害が生じる可能性あるよね」という「知見」を事前に共有しておけ、ということだろう。
最後に
次は不法行為の法理だね。で、信託見て会社法見て陪審諸々見て、って感じか。
ということで、こちらのパブリックメモも終了です。最後までお読みいただき、ありがとうございます。

